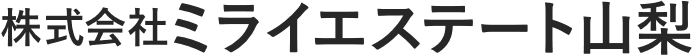2025年 建築基準法改正 これからの新しい家は〝省エネ〟性能向上へ

建築基準法は、私たちの暮らしと密接に関わる建物の安全や品質を保つための大切な法律です。2025年には、この建築基準法が改正され、いくつかの点が新しくなります。
今回は、改正のポイントの概要をわかりやすく解説し、私たちの暮らしにどのような影響があるのかご紹介します。
1、建築物の省エネ基準適合義務化:光熱費削減と快適な暮らし
2025年4月1日以降に新築される住宅や建築物は、原則として省エネ基準への適合が義務付けられます。これは、地球温暖化対策の一環として、建物のエネルギー消費量を減らすことを目的としています。
日本のエネルギー消費の約3割を占める建築物分野での省エネ対策として、建物の省エネ基準が強化されました。
具体的には、断熱性能の向上や高効率な設備の使用などが求められます。
- 断熱性能の向上:壁や屋根、窓などの断熱材を強化することで、建物内部の温度変化を抑制し、冷暖房費を削減します。例えば、高性能な断熱材を使用したり、複層ガラスの窓を採用したりすることが考えられます。
- 高効率な設備の使用:高効率なエアコンや給湯器、照明器具などを導入することで、エネルギー消費量を削減します。例えば、省エネ性能の高いLED照明や、ヒートポンプ式の給湯器などが挙げられます。
これらの措置により、住宅の光熱費削減や快適な居住環境の実現が期待できます。
具体的には、地域区分6のエリアでは、断熱等性能等級4以上、一次エネルギー消費量等級4以上です。現在の長期優良住宅が最低基準となります。
また、5年後の2030年にはさらに基準が引き上げられて、断熱等性能等級5以上、一次エネルギー消費量等級6以上のZEH基準の水準となります。
2、4号特例の縮小:建築物の安全性向上
これまで、一定の条件を満たす小規模の建築物(4号建築物)については、構造計算や確認申請の手続きが簡略化されていました。しかし、今回の改正では、この4号特例が縮小されます。
これにより、構造計算が必要となる建築物が増えますが、これは、建物の安全性を確保するための措置です。
身の回りの事例として、山梨県の場合、都市計画区域外が多く、建築確認申請が必要ありませんでした(何らかの形で届け出る場合が多い)。今回の改定で、都市計画区域外の木造住宅でも、平屋建てかつ200㎡以下の場合を除き、建築確認申請が必要になります。
3、木造建築物の構造計算基準等の見直し:木造建築の可能性を広げる
近年、大規模な木造建築物が増加しています。今回の改正では、木造建築物の構造計算基準や防火規定が見直されます。
これにより、木造建築物の設計・施工の自由度が高まるとともに、更なる安全性の確保が図られます。
木造建築の省エネ化によって、建物が重くなることにも対応するため、壁量計算の方法や柱の小径基準が見直されます。
4、 その他:既存建築物の省エネ改修促進、バリアフリー化推進
上記以外にも、以下の点が改正されます。
- 既存建築物の省エネ改修の促進:既存の建築物の省エネ改修を促進するための制度が拡充されます。
- 建築物のバリアフリー化の推進:高齢者や障害者の方々がより快適に利用できる建築物の設計が求められます。
- 建築物の維持保全計画の作成義務化:建築物の適切な維持管理を促進するため、定期的な点検や修繕計画の作成が義務付けられます。
これらの改正は、私たちの暮らしや建築業界に大きな影響を与える可能性があります。
より安全で持続可能な社会へ
2025年の建築基準法改正は、省エネ化や安全性向上など、より良い社会の実現を目指したもので、持続可能な社会を実現するための重要な一歩となります。
今回のコラムでは、主な改正点をご紹介しましたが、詳細については国土交通省のウェブサイトなどでご確認ください。
※国土交通省Webサイト
https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_001001.html