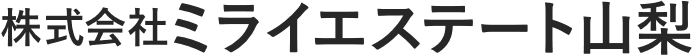2025年現在、『インフレ局面を知ろう!!』

2025年現在、私たちの生活は「インフレ」という大きな経済のうねりの中にあります。スーパーでの買い物、ガソリン代、電気料金――あらゆるモノやサービスの値段が上がり、「昨日と同じ1万円札なのに、今日買えるものは少なくなった」と感じる場面が増えているのではないでしょうか。
このインフレという状況は、一体何を意味するのでしょうか。そして、人生最大の買い物である「家」の購入において、どのような影響を及ぼすのでしょうか。
ここでは、インフレの基本をわかりやすく解説し、この特殊な経済局面で住宅を購入することの「光と影」を多角的に解説していきます。
目次
インフレとは何か? なぜ不動産が注目されるのか?
インフレ(インフレーション)とは、モノやサービスの価値が継続的に上昇し、相対的にお金の価値が下がる経済現象のことです。昨日100円で買えたパンが今日110円になる、これがインフレです。手元の100円玉の価値は変わらなくても、その購買力は低下してしまいます。
このような状況下で、資産防衛の手段として「不動産」が注目されるのには明確な理由があります。不動産は、現金や預貯金といった金融資産とは異なり、土地や建物という実体を持つ「実物資産」だからです。
インフレが進むと、物価全体の上昇に伴い、家を建てるための資材費や人件費といった建築コストも上昇します。その結果、新築住宅の価格が上がり、それに引きずられる形で中古住宅の価格も上昇する傾向にあります。つまり、お金の価値が下がっても、不動産の価値は下がりにくい、あるいは一緒に上昇していくため、インフレに強い資産とされているのです。
この基本原則を踏まえた上で、インフレ基調の今、家を買うことの具体的なメリットとデメリットを見ていきましょう。
インフレ局面に家を買う「メリット4選」
1. 資産価値の目減りを防ぐ「インフレヘッジ」になる
最大のメリットは、資産防衛です。インフレ下で現金を銀行に預けておくと、その価値は物価上昇のペースに合わせて実質的に目減りしていきます。しかし、不動産という実物資産に換えておくことで、資産価値が物価上昇に連動し、価値の目減りを防ぐ効果(インフレヘッジ)が期待できます。
2. 住宅ローン残高が「実質的に」軽くなる
住宅ローンという巨額の借金も、インフレ下では見え方が変わります。例えば30年前に3,000万円のローンを組んだとします。当時の3,000万円と現在の3,000万円では、お金の価値が全く異なります。インフレによって物価や賃金が上昇すれば、過去に借りた3,000万円という金額の返済負担は、相対的に軽くなるのです。これは、将来の収入増を見込める現役世代にとっては特に大きなメリットと言えるでしょう。
3. 将来の家賃上昇リスクから解放される
インフレは、当然ながら家賃にも影響を及ぼします。物価や人件費が上がれば、大家さんも家賃を上げざるを得ません。賃貸に住み続ける限り、この家賃上昇リスクからは逃れられません。一方、持ち家であれば、住宅ローンを固定金利で組んでいれば返済額は完済まで一定です。将来の住居費を確定させ、インフレの波から生活を守る砦となるのです。
4. 建築費がさらに高騰する前に購入できる
「待てば安くなるかもしれない」という期待は、インフレ基調では通用しにくいかもしれません。ウッドショック以降、建築資材の価格は高止まりしており、さらに円安や人手不足による人件費の上昇も重なり、建築コストは今後も上昇傾向が続くと予測されています。この状況では、「今日が一番安い日」という考え方も成り立ちます。購入を先延ばしにすればするほど、同じ家でもより高い金額を支払うことになる可能性があるのです。
インフレ局面に家を買う「デメリット4選」
1. 住宅ローン金利の上昇リスク
インフレと金利はシーソーのような関係にあります。行き過ぎたインフレを抑制するため、日本銀行は政策金利を引き上げる金融引き締めを行います。政策金利が上がれば、住宅ローンの金利も上昇します。特に、現在主流の変動金利型ローンを選んでいる場合、将来の金利上昇によって毎月の返済額が増え、家計を圧迫するリスクを直接的に負うことになります。
2. 不動産価格の「高値掴み」リスク
インフレで不動産価格が上昇しているということは、裏を返せば「割高な価格で買ってしまう」リスクがあるということです。もし将来、インフレが収束し、金融引き締めによって景気が後退する局面が来れば、不動産需要が減退し、価格が下落に転じる可能性もゼロではありません。購入した時が価格のピークで、その後資産価値が下落してしまう「高値掴み」のリスクは、インフレ局面での購入における最大の懸念点の一つです。
3. 建築コスト高騰による購入価格の上昇
メリットの裏返しになりますが、建築コストが上昇しているため、そもそも住宅の販売価格が高くなっています。同じ品質の家でも、数年前に比べて数百万円単位で高くなっているのが現実です。予算内で希望の家を見つけること自体の難易度が上がっています。
4. 生活費全般の上昇による家計への負担増
インフレは住宅だけでなく、食費や光熱費など、生活に関わるあらゆるコストを押し上げます。ただでさえ日々の生活費が増加している中で、高額な住宅ローン返済が始まると、家計の余裕が著しく失われる可能性があります。住宅購入後の生活まで見据えた、慎重な資金計画が不可欠です。
結論:2025年現在、『インフレ局面を知ろう!!』
インフレ基調における住宅購入は、大きなチャンスとリスクが同居する、まさに諸刃の剣と言えます。では、私たちはどう判断すればよいのでしょうか。
結論は、「インフレだから買う」「インフレだから見送る」という短絡的な二元論に陥らないことです。重要なのは、この経済状況を正しく理解し、自分自身のライフプランと照らし合わせて「戦略的に」判断することです。
- 金利リスクをどうコントロールするか?:将来の金利上昇が不安であれば、当初の金利は高くても返済額が確定する「固定金利」を選ぶ。リスクを取ってでも当初の返済額を抑えたいなら「変動金利」を選ぶ。この選択が、将来の家計を大きく左右します。
- どの物件を選ぶか?:すべての不動産がインフレに強いわけではありません。人口が増加し、賃貸需要が安定している都市部や利便性の高いエリアの物件は価値が維持されやすい一方、そうでないエリアはインフレ下でも価値が下落するリスクがあります。
- 自分自身の家計の体力は十分か?:将来の金利上昇や生活費の上昇を見越して、無理のない返済計画を立てることが何よりも重要です。
インフレという荒波は、資産の価値を揺さぶる脅威であると同時に、賢明な航海術を身につけた者にとっては、資産形成の追い風にもなり得ます。情報を吟味し、リスクを直視し、そして自らの計画に自信が持てた時こそが、あなたにとっての「買い時」なのかもしれません。
ご参考に。