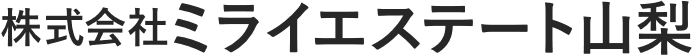日本の木造住宅は、なぜ寒いと感じる?!

日本の木造住宅は、なぜ寒いと感じる?!
昔ながらの在来工法で建てられた木造住宅は、結構寒いと感じられます。他の先進国に比べても寒いと言われますし、他の構造、例えば鉄筋コンクリート造のマンションと比べても寒いと言われます。
今回は、日本の木造住宅が寒いと言われる理由について、掘り下げていきます。
1、日本の木造住宅が寒いと感じる主な理由
日本の木造住宅が寒いと感じる理由は、いくつかの要因があります。
1,断熱性の低さ
特に築年数の古い木造住宅においては、断熱材が十分に充填されていない、あるいは全く使用されていない場合があります。断熱性能が低いと、外の冷たい空気が室内に伝わりやすく、室内の暖かい空気は外へ逃げやすいため、室温を維持することが困難になります。
2,気密性の低さ
木造住宅は、構造、性質上の特性や建築時の施工精度などにより、どうしても建物に隙間ができやすい傾向があります。特に古い住宅では、窓やドアの建て付けが悪くなったり、壁や床にも隙間が生じていることが少なくありません。これらの隙間から冷たい外気が容赦なく侵入し、暖房で温めた室内の空気を奪っていくのです。
3,コールドドラフト現象
冷たい外気は、窓ガラスや外壁を冷やし、その冷やされた空気が下降気流となって足元に流れ込んできます。これがコールドドラフト現象であり、特に断熱性能の低い窓や外壁を持つ古い木造住宅では顕著に現れ、底冷えの原因となります。
4,開口部からの熱損失
住宅の中で最も熱の出入りが大きいのが窓です。日本の住宅では、窓の断熱性能が低い場合が多く、冬には室内の熱が窓を通して大量に逃げてしまいます。およそ58%の熱が流失すると言われています。反対に、夏には外からの熱が侵入しやすい原因にも繋がり、約73%の熱が流入してくると言われています。
5,構造的特性
木材自体は熱を伝えにくい性質を持っています。でも、気密性や断熱性が不十分な場合、一度冷えてしまうと再び温まりにくいという特性が寒さを助長してしまいます。
特に、古い木造住宅では、断熱性の低いアルミサッシに単板ガラス(シングルガラス)が使われていて、外気温の影響をダイレクトに室内に伝えてしまいます。近年では、ペアガラスやトリプルガラス、断熱性の高い樹脂サッシなどが普及していますが、既存の住宅では依然として断熱性能の低い窓が多く使われています。
木造住宅に対して鉄筋コンクリート造の住宅は、型枠にコンクリートを流し込み固める工法の為、隙間が生じにくく気密性が高いと言われています。気密性の高さで、木造住宅の方が寒いと感じるのでしょう。ただし、熱伝導率はコンクリートの方が高いので、断熱性能的には木造の方が高いと言えます。しかも、断熱性能を高めるための費用が抑えられます。
2、寒さ対策のヒント
木造住宅の寒さ対策として以下のような方法あります。
1,断熱リフォーム
壁や床下、天井などに断熱材を追加することで、住宅全体の断熱性能を向上させることができます。
2,気密性を向上させる
窓やドアの隙間を気密テープやシーリング材で塞ぐことで、隙間風の侵入を防ぎ、暖房効率を高めることができます。
3,高性能な窓の導入
ペアガラスやトリプルガラス、Low-Eガラスなどの断熱性の高い窓に交換することで、熱損失を大幅に減少させることができます。従来のサッシにペアガラスなどの厚みのあるガラスを直接入れられない場合が多く、その場合はアタッチメントをかますことによりペアガラスを取り付けることができます。
また、既存のアルミサッシの内側にもう一つ窓を設ける方法があります。この二重窓は、断熱性と気密性を向上させる効果的な方法です。
アルミサッシをまるごと樹脂サッシとLow-Eペアガラスに付け替えれば、最新の窓の性能を手に入れられます。
4,断熱シートやフィルム、カーテンの利用
窓ガラスに断熱シートやフィルムを貼ったり、厚手の断熱カーテンを使用したりすることでも、熱の出入りを抑えることができます。この方法が、大きな工事も必要なく手ごろな方法です。
3、日本の住宅性能の現状と未来
日本の住宅性能は、世界的に見ると低い水準にあると言われています。日本の住宅は断熱性能に関する基準が緩く、義務化もされていません。
例えば、ドイツでは住宅の断熱性能が厳格に義務付けられており、その基準は日本の現行基準よりもはるかに高くなっています。
しかし、日本でも住宅性能向上の動きは着実に進んでいます。2025年の建築基準法改正では、全ての新築住宅に対して省エネ基準への適合が義務付けられ、具体的には断熱等級4以上、一次エネルギー消費量等級4以上を満たす必要があります。これは、従来の基準に比べてエネルギー消費量を20%から30%程度削減する効果が期待されています。
さらに、2030年にはより厳しい基準(断熱等級5以上、一次エネルギー消費量等級5以上)が適用される予定であり、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)基準に相当する住宅が普及していくことが見込まれています。
ZEH基準は、太陽光発電などの省エネ設備を設置することで、年間の一次エネルギー消費量を実質ゼロにすることを目指しているので、より高い断熱性能と再生可能エネルギーの導入が求められます。
4、欧米先進国の例
ドイツ
- ・厳格な基準:ドイツでは、住宅の断熱性能に関する基準が非常に厳しく、建築基準法に基づいて義務化されています。例えば、2025年から日本で義務化される断熱等級4(UA値0.87)に対して、ドイツの基準はそれよりもはるかに厳しく、UA値が0.2 W/m²K以下であることが求められています。
- ・エネルギー効率:ドイツでは、エネルギー効率を高めるために、住宅の設計段階からエネルギー消費を考慮し、再生可能エネルギーの利用も促進されています。これにより、住宅のエネルギー消費量を大幅に削減することが目指されています。
スウェーデン
- ・室温基準:スウェーデンでは、住宅の室温を最低でも18℃以上に保つことが法律で定められています。これにより、住民の健康を守ることが重視されています。
- ・断熱性能:スウェーデンの住宅は、断熱材の厚さや窓の性能に関しても厳しい基準が設けられており、これにより冬季の暖房効率が高まります。
アメリカ
- ・エネルギー効率基準:アメリカでは、国のエネルギー政策に基づいて州ごとに異なるエネルギー効率基準が設定されております。例えば、エネルギー効率基準は、住宅の設計や建設において、エネルギー消費を最小限に抑えることを目的としています。
- ・LEED認証:環境に配慮した建物には、LEED(Leadership in Energy and Environmental Design)認証が与えられ、これによりエネルギー効率や環境への影響が評価されています。
欧米の先進国は、緯度的に北海道より北の国が多く、どの国も高い住宅性能基準が設けられています。日本でも、北海道の地域区分1や2においては、ZEH基準のUA値が0.4以下とされていて、欧米諸国に近いものがあります。それでも、今回の2025年基準のUA値が0.87以下、2030年基準のUA値が0.60以下(東京などの地域区分6)は、まだまだ差が大きいため、日本の気候を考慮しながら、より近付けていけるようにしていくべきでしょう!