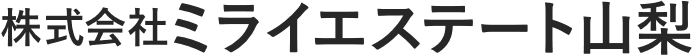戸建ての査定額は、基本「土地」と「建物」の足し算!

目次
なぜ不動産屋によって査定額が違うの?
マイホームの売却を考えたとき、誰もが抱く「我が家はいったいいくらで売れるのだろう?」という大きな期待と少しの不安。いざ、複数の不動産会社に査定を依頼してみると、会社によって数十万円、ときには数百万円も違う金額が提示され、「一体どれが本当の価格なの?」と混乱してしまった経験はないでしょうか。
この価格差は、決して不動産会社が“勘”や“適当”で値段をつけているからではありません。一見するとブラックボックスに見える不動産査定の世界には、実は全国共通のしっかりとした評価ルールが存在します。そして、価格に差が生まれるのにも、ちゃんとした理由があるのです。
ここでは、プロが使う戸建て査定の「基本」を、専門用語をかみ砕きながら解説していきます。この仕組みさえ分かれば、不動産会社が提示する査定額の根拠を理解し、納得感を持って大切な資産の取引を進めることができるはずです。
1、大原則は「土地」と「建物」の分離評価
戸建て査定の最も重要な大原則、それは「土地の価値」と「建物の価値」を、全く別々のモノサシで測り、最後にそれらを足し算(合算)することです。マンション査定とは異なり、この「分離評価」が戸建て査定のすべての出発点となります。
- 土地の価値は、主に「市場性」で決まります。これは、平たく言えば「その場所が、今どれだけ人気があるか」ということです。周辺でどんな家がいくらで売れているか、という市場の動向が価格を大きく左右します。
- 建物の価値は、主に「費用性」で決まります。これは、「もし同じ建物を今新築したらいくらかかり、そこからどれだけ古くなったか」という視点です。
このように、土地と建物では価値を測るモノサシが全く異なります。この2つの評価方法を理解することが、査定の謎を解く第一歩となるのです。
2、【土地編】ご近所相場がすべて!「取引事例比較法」
土地の価格を決める主役となるのが、プロの世界で「取引事例比較法」と呼ばれる手法です。これは非常にシンプルです。「あなたの家の近所で、似たような条件の土地が最近いくらで売れたか?」という実際の取引価格(成約事例)を基準に価値を判断する方法です。市場でのリアルな取引価格を基にするため、最も客観的で信頼性が高いとされています。
ステップ1:お手本(取引事例)を探す
不動産会社は、まず「REINS(レインズ)」という業者専用のデータベースシステムにアクセスします。ここには、過去にどの不動産がいくらで成約したかという、信頼性の高い情報が蓄積されています。査定担当者は、この中からあなたの土地と条件が近い事例を複数ピックアップし、査定の土台とします。
ステップ2:個性や違いを調整する「補正作業」
世の中に全く同じ土地は二つとありません。そのため、お手本となる取引事例とあなたの土地との間に存在する様々な違いを調整する「補正」という作業が行われます。ここがプロの腕の見せ所であり、査定額に差が生まれる最大のポイントです。
- 時点修正: 不動産価格は常に変動しています。もし参考にする事例が1年前のもので、その間に周辺の地価が5%上昇していれば、事例の価格も5%上乗せして現在の価値に直します。
- 事情補正: 「相続した土地で、とにかく早く現金化したかったから相場より安く売った」など、取引に特殊な事情があった場合は、その影響を取り除き、通常の取引だった場合の価格に補正します。
- 個別要因の比較: ここが最も複雑で、専門的な判断が求められる部分です。
- 立地: 最寄り駅からの距離(徒歩1分=80mで計算)、スーパーや学校、公園などの利便施設の有無、逆に騒音や臭いの元になるような嫌悪施設の有無など。
- 道路付け: 日当たりの良い南向きの道路に面しているか、開放感のある角地か、車の出し入れがしやすい広い道路か、といった点は価格に大きく影響します。
- 土地の形状: きれいな長方形(整形地)は評価が高く、使いにくい三角形の土地や、道路への出入り口が狭い旗竿地(不整形地)は評価が下がります。
これらの要素を一つひとつ比較し、「プラス5%」「マイナス10%」といったように価格を調整していくのです。
【自分でできる!】我が家の土地相場を掴む裏ワザ
専門家でなくても、土地価格の大まかな目安を知る方法があります。それは国税庁が公開している「路線価図」を見ることです。これは主に相続税の計算に使われるものですが、実勢価格の約8割の水準で設定されているため、以下の式で市場価格の目安を推測できます。
実勢価格の目安 ≒ 路線価 ÷ 0.8
例えば、自宅前の道路に「150D」と書かれていれば、1㎡あたり15万円が路線価です。これを0.8で割り戻すと18.75万円。これに土地の面積を掛ければ、大まかな土地の市場価格が把握できます。
3、【建物編】新品価格からの引き算!「原価法」
土地とは対照的に、建物の価値は「原価法」という手法で評価されます。これは非常に分かりやすい考え方で、「今、あなたの家と全く同じものを新築したらいくらかかるか?」という価格(再調達原価)を算出し、そこから年月が経って古くなった分を差し引いていく(減価修正)というものです。
ステップ1:「新品価格(再調達原価)」を計算する
まず、「もし今、この家を建て直したら?」という費用を算出します。これは以下の式で計算されます。
再調達原価 = 標準的な建築単価 × 延床面積
建築単価は建物の構造によって異なり、一般的な木造住宅であれば1㎡あたり15万円~20万円程度が目安とされています。
ステップ2:「古くなった分(減価修正)」を差し引く
次に、新品価格から築年数に応じた価値の減少分を差し引きます。この計算の基準となるのが「法定耐用年数」です。これは税法上で定められた「資産として価値がある期間」のことで、一般的な木造住宅の場合は22年とされています(居住用の場合33年を使う場合もあります)。
簡単な計算式は以下の通りです。
建物評価額 = 再調達原価 × (残りの耐用年数 ÷ 全体の耐用年数)
例えば、築11年の木造住宅であれば、耐用年数の半分が経過しているので、価値は新品価格の半分(残耐用年数11年 ÷ 全耐用年数22年)と計算されます。
【要注意】「築22年超えの木造住宅は価値ゼロ」のウソ・ホント
この計算方法から、日本の不動産市場では「法定耐用年数である22年を超えた木造住宅の価値はゼロ」と査定される慣行があります。場合によっては、解体費用として土地の価格からマイナスされることさえあります。
しかし、これはあくまで税務上の考え方に基づいた画一的な評価です。実際には、適切なリフォームや丁寧なメンテナンスが行われていれば、築22年を超えても建物の価値が認められるケースは十分にあります。査定を依頼する際は、リフォーム履歴や設備の更新状況などを積極的にアピールすることが、正当な評価を得るために非常に重要です。
結論、戸建ての査定額は、基本「土地」と「建物」の足し算!
戸建ての査定額とは、「土地の市場価値(取引事例比較法)」と「建物の現在価値(原価法)」を丁寧に算出し、最後にそれらを合算した金額です。
不動産会社によって査定額が違うのは、特に土地の「個別要因の比較」(例:この眺望をプラス5%と見るか、10%と見るか)や、建物の「メンテナンス状態の評価」といった、専門家の経験や知見が反映される部分での解釈が異なるからです。
これからは、不動産会社から査定書を受け取ったら、ただ総額を見るだけでなく、一歩踏み込んで、こう質問してみてください。
「この査定額のうち、土地と建物の内訳はそれぞれいくらですか?」
「土地の価格は、どの取引事例を参考に、どのように補正しましたか?」
その質問に対して、論理的で分かりやすい答えを返してくれるかどうかが、あなたが信頼できるパートナーを見つけるための重要な試金石となります。査定の仕組みを理解することは、あなたの大切な資産を守り、後悔のない不動産取引を実現するための、最強の武器になるのです。
最後に、不動産売却の際に使われる「不動産一括査定サイト」についてですが、基本、考え方は変わりません。よく、ビッグデータといいますが、おそらく膨大なデータを元に算出されていると思います。膨大なデータを元にしていると、どんどん平均化されて、特出した数字は出にくいはずなのですが、広告で「えっ、こんなに・・・」なんて言っているのはなぜでしょう。
複数の「不動産一括査定サイト」に依頼した場合、平均化された代わり映えのしない机上査定価格を提示され、詳しく査定するためには現地を見せてくださいと依頼した数だけ電話が鳴ります。ご注意ください。