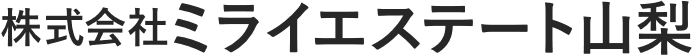不動産表示① 『徒歩〇分』


不動産広告や資料として渡される図面には、△△まで『徒歩〇分』と表示されています。
既に、かなりの方がご存じかと思われますが、通常【1分=80m】で計算されています。
今回は、〝分数表示〟について、もう少し深掘りします。
- 1、なぜ徒歩1分が80mなのか?
この基準は、なんと健康なハイヒールを履いた女性が実際に歩いて決められたとのこと!
この平均が、約80.3m/分!!
にわかに信じがたい気もしますが、これを基準に【1分=80m】とされました。
東京のオフィス街の出勤時にでも計ったのでしょうか・・・
不動産業界では、通常、この【1分=80m】で単純に計算されています。
- 2、どこからどこまでの距離を?
例えば、「△△小学校徒歩〇分」の場合、〝どこからどこまでの距離〟を測っているのでしょうか?
通常、家の駅に一番近い端から小学校の敷地の一番手前の端までの距離を【1分=80m】で割ります。
ちなみに、私の場合は〝家の前から小学校の校門〟までを計っています。
昔は、ゼンリンの住宅地図で一番近いと思われるルートの距離を定規で計り、【1分=80m】で割っていましたが、現在はGoogleマップ(航空写真)で小学校の校門の位置を確認し、そこの前までの距離をGoogleマップで計測、それを【1分=80m】で割っています。
よくある不動産サイトでは、物件の位置を登録して〇km圏内の施設と指定すると学校やスーパー、駅などの距離が自動で表示され、それを使う場合もあります。ただ、手順的に自分たちで物件を調査し、資料を作ってからサイトに登録するケースが多いので、Googleマップで計測する方が多くなります。
でも、ある不動産サイトでは、561mのように1m単位で距離が出てきます。次の話に繋がりますが、この〝1m〟がポイントになる場合があります。
結論から言いますと、サイトの計測ならサイトの計測で、Googleマップで計測ならGoogleマップで計測基準を合わせて表示しています。
3、実際の計算方法は?
単純に計った距離を【1分=80m】で割ります。
例えば、
△△小学校まで560mだったとします。【1分=80m】で割ると7分となります。
これが、561mだったとすると、厳密に言えば8分となるわけです。
割った端数を切り上げるからです。
ただ、Googleマップで計測すると細かくても10m単位なので、560mなら7分、570mなら8分と表示しています。
・560m ÷ 80m/分 = 7分
・570m ÷ 80m/分 = 7.125分 ・・・ 8分
では、私たちの住む山梨県のように、最寄り駅が遠く、△△駅6.1kmなんて表示も少なくありません。これを徒歩77分と表示したりしますが、なかなか77分は歩かないので、ピンときません?!その場合は、感覚的にわかりやすい6.1kmで表示しています。
また、距離がある「車で〇分」と表示したりします。
「車で〇分」の場合も決められていて、車の場合【1分=400m】で計算されています。上記の場合は、「車で16分」となります。
・6.1km ÷ 400m/分 = 15.25分 ・・・ 16分
徒歩 【1分=80m】
車 【1分=400m】
※補足・・・私たちの住む山梨県のように、中学校まで自転車で通学する場合があります。その場合、決められた数値ではありませんが、自転車1分240mで計算し、お客様には〇分程度ですと話をします。
- 4、注意点
この分数表示の注意点は、
- ①信号待ち
- ②踏切待ち
- ③坂道等のアップダウン
これらは考慮されていません。含まなくても良いとされています。
「徒歩」における注意点
おそらく、山梨では歩くスピードがもう少しゆっくりかもしれません。
特に学校への分数は、子供のことなので、もう少し長めに考えた方が良いでしょう。中学校は、2km以上あると自転車になります。その場合、参考値として1分240mで計算してみてください。特に、自転車通学の微妙なラインにはお気を付けください。この通りまでは徒歩、これを超えると自転車みたいなことがあります。
「車」における注意点
【1分=400m】ですが、時速(60分)換算してみると24kmです。私たちの住む山梨県では、体感として、表示されている分数より早く着くと思います。中心街から少し離れると信号も減りますし、ない場合もあります。なにせ、通勤時間のラジオの交通情報で、500mとか1kmでも渋滞となるので。