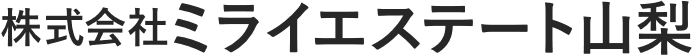『現在の政策金利の上昇は、まだ、正常な状態に戻す治療中!』

2025年8月、日本の経済と住宅市場は歴史的な岐路に立たされています。数十年にわたる超低金利政策からの脱却を目指す日本銀行(日銀)の金融政策「正常化」は、住宅購入を検討する者にとって、期待と不安が交錯する複雑な環境を生み出しているのです。長らく続いた「ゼロ金利」という異常な状態が終わりを告げ、金利が本来の機能を取り戻しつつある今、住宅ローンのコストは上昇基調にあります。
この転換期をさらに複雑にしているのが、米国で再燃する「トランプ関税」に代表される海外経済の不確実性です。この外部からの逆風は、日本の輸出産業に影を落とし、景気全体の下振れリスクとなります。日銀は、国内の賃金と物価の好循環を確認しつつも、この不透明な国際情勢を慎重に見極めるため、利上げのペースを一時的に緩めています。しかし、追加利上げへの意欲は依然として示されており、金利が今後さらに上昇するであろう「金利上昇局面」にあることは間違いありません!
このような状況下で家を買うことは、極めて重大な決断となります。金利の上昇は、月々の返済額を直接的に増加させる一方で、過熱した不動産価格を抑制し、購入者にとっては価格交渉の好機をもたらす可能性も秘めています。
ここでは、金利上昇という新たな時代に住宅購入を検討する人々に向けて、マクロ経済の動向から具体的なリスクを分析し、賢明な意思決定を下すための羅針盤となれればと考えています。
1、日銀はなぜ利上げに踏み切るのか
日銀の利上げは、単なる金融政策の変更ではなく、日本経済を長期的な健全性へと導くための構造的な転換です。その背景には、大きく分けて「金融政策の正常化」という大目標と、「インフレ抑制」および「円安是正」という二つの具体的な目的が存在します。
A. 金融政策「正常化」への道
現在の利上げは、長年続いたマイナス金利政策やイールドカーブ・コントロール(YCC)といった非伝統的な金融緩和策、すなわち「異常な状態」から脱却し、金利が市場メカニズムを通じて経済を調整する「正常な状態」へと回帰させるプロセスの一環です。2024年3月、日銀はマイナス金利政策の解除を決定し、17年ぶりとなる利上げに踏み切りました。これは、金融政策の正常化に向けた歴史的な第一歩となりました。
正常化の目的は、主に二つあります。
第一に、極端に低い金利は金融市場の機能を歪め、企業の生産性向上を阻害するなどの副作用をもたらしてきました。金利機能を回復させることで、より効率的な資金配分を促し、経済の新陳代謝を高める狙いがあります。
第二に、政策金利がゼロ近辺にあると、将来的な景気後退期に「利下げ」という最も伝統的で強力な金融緩和手段を講じる余地がなくなります。金利をある程度の水準まで引き上げておくことは、将来の経済危機に備えるための「政策の弾力性」を確保する上で不可欠なのです。
B. 利上げの二大目的!インフレ抑制と円安是正
日銀が利上げを進める直接的な理由は、物価と為替という二つの課題に対応するためです。
第一の目的は、インフレの抑制です。経済が活発になりすぎると、モノやサービスへの需要が供給を上回り、物価が継続的に上昇するインフレが加速します。
日銀は、企業の設備投資や個人の消費といった経済活動を抑制するために、お金を借りる際のコストである金利を引き上げ、過熱した景気を冷まし、物価の安定を図るのです。特に日銀が目指しているのは、賃金の上昇を伴った持続的かつ安定的な2%の物価上昇の実現であり、利上げはこの目標達成が視野に入ったことの証しとも言えます。
ここで重要なのは、日銀が「良いインフレ」と「悪いインフレ」を区別しようとしている点です。
賃金上昇が需要を牽引する「良いインフレ」は経済にとって望ましいが、円安による輸入物価の高騰が引き起こす「悪いインフレ」は、国民生活を圧迫すると考えられています。日銀の利上げは、「良いインフレ」の定着を確認しつつ、「悪いインフレ」の要因となる過度な円安を是正するという、極めて繊細な舵取りを求められているのです。
第二の目的は、この円安の是正です。日本の超低金利政策が続く一方で、米国などが大幅な利上げを行った結果、日米の金利差が拡大しました。これが、より高い利回りを求める投資家による「円売り・ドル買い」を加速させ、歴史的な円安を招きました。円安は輸出企業にとっては追い風となりますが、エネルギーや食料品の輸入価格を押し上げ、国民生活に大きな負担を強いります。日銀が利上げを行うことで日米金利差を縮小させれば、円の魅力が高まり、円安に歯止めをかける効果が期待されます。
C. 不確実性要因:「トランプ関税」という衝撃
この正常化への道を複雑にしているのが、「トランプ関税」という外部からの衝撃です。米国の関税政策は、日本の自動車や鉄鋼といった主要な輸出産業に直接的な打撃を与え、経済成長を押し下げるリスクとなっています。
この状況は、日銀を極めて難しい立場に追い込んでいます。国内のインフレを抑制するために利上げを急げば、関税によって弱体化した企業活動に追い打ちをかけ、景気後退を引き起こし兼ねません。一方で、利上げを見送れば円安がさらに進行し、輸入インフレが国民生活を苦しめ続けることになります。まさに「前門の虎、後門の狼」というわけです。
このため、日銀は「不確実性が極めて高い」として、関税政策の具体的な影響を見極めるまで追加利上げに慎重な姿勢を示しています。これは、中央銀行の金融政策が、国内の経済指標だけでなく、海外の一国の政治的な動向に大きく左右されるという新たな現実を示しています。
住宅購入者にとって、これは将来の金利動向の予測が、純粋な経済予測から、より不確実性の高い政治予測の要素を含むようになったことを意味し、一層の注意が必要となっています。
2、金利上昇がもたらす複合的リスク
マクロ経済レベルでの金利上昇は、住宅購入を検討する個人にとって、具体的かつ多岐にわたるリスクとなって現れます。これらのリスクを正しく理解し、備えることが賢明な意思決定の第一歩となります。
A. リスク1:住宅ローン返済負担の増大
最も直接的で影響の大きいリスクは、住宅ローン返済額の増加です。日銀が政策金利を引き上げると、それに連動して民間の金融機関も住宅ローンの基準金利を引き上げます。。住宅ローンは何十年にもわたる高額な借金であるため、わずか数パーセントの金利上昇でも、総返済額に与える影響は絶大です。
以下のシミュレーションは、金利上昇が返済額に与えるインパクトを具体的に示しています。
表1:金利上昇シミュレーション:月々返済額と総返済額への影響
(借入額4,000万円、返済期間35年、元利均等返済の場合)
| 借入金利 | 月々返済額 | 年間返済額 | 総利息支払額 | 総返済額 | 当初からの増加額 |
| 0.5% | 103,834円 | 1,246,008円 | 3,608,582円 | 43,608,582円 | – |
| 1.0% | 112,780円 | 1,353,360円 | 7,367,939円 | 47,367,939円 | +3,759,357円 |
| 1.5% | 122,234円 | 1,466,808円 | 11,338,409円 | 51,338,409円 | +7,729,827円 |
| 2.0% | 132,187円 | 1,586,244円 | 15,518,485円 | 55,518,485円 | +11,909,903円 |
この表が示すように、金利が0.5%から1.5%へと1%上昇するだけで、総返済額は約773万円も増加します。この増加分は、家計の可処分所得を直接的に圧迫し、教育費や老後資金といった他のライフプランに深刻な影響を及ぼす可能性があるのです。
B. リスク2:不動産価格の下落
一般的に、金利と不動産価格は逆相関の関係にあり、金利が上昇すると不動産価格は下落する傾向があります。このメカニズムは主に二つの要因によって説明されます。
- 住宅需要の減少:住宅ローン金利が上昇すると、購入者の返済負担能力が低下します。同じ月々の返済額で借りられる金額が減るため、より低価格の物件しか検討できなくなったり、購入自体を断念したりする人が増え、これにより市場全体の需要が減退し、価格下落圧力となるのです。一部のアナリストは、理論上、金利が1%上昇すると不動産価格は20%下落する可能性があると試算しています。
- 不動産供給の増加:金利上昇は、特に変動金利でローンを組んでいる既存の住宅所有者に影響を与えます。返済額の増加に耐えられなくなった人々が、自宅の売却を余儀なくされるケースが増加し、これにより中古物件の供給が増え、需給バランスが崩れることで、さらなる価格下落を招くことがあります。
この不動産価格の下落は、一見すると購入者にとって有利に思えるかもしれませんが、ここには「買い手のパラドックス」とでも言うべき罠が潜んでいます。価格が下落するのを待っている間に、金利はさらに上昇している可能性が高いのです。結果として、安くなった物件を高金利のローンで購入することになり、総返済額では以前より不利になるという事態も十分に考えられます。不動産価格の下落は、単なる「お買い得」のサインではなく、借入コストの上昇と経済の不確実性の高まりというリスクの裏返しでもあるのです。
C. リスク3:ローン審査の厳格化
金利上昇局面では、金融機関は貸し倒れリスクを警戒し、住宅ローンの審査基準を厳格化する傾向があります。返済負担率(年収に占める年間返済額の割合)の基準を厳しくしたり、より多くの自己資金(頭金)を求めたり、借入期間を短く設定したりすることが考えられます。
これは、たとえ希望の物件を見つけ、価格交渉に成功したとしても、そもそも必要な額のローンを借りられないというリスクが高まることを意味するのです。特に、収入に対して借入希望額が大きい場合や、他の借り入れがある場合には、審査がより一層厳しくなることが予想されます。
これらのリスクは、個別に存在するだけでなく、相互に影響し合っています。
例えば、金利上昇による返済負担増は、家計の消費を抑制します。住宅ローン利用者の7割以上が変動金利を選択している現状を考えると、金利が1%上昇した場合、マクロ経済全体で年間約1兆円規模の個人消費が抑制されるとの試算もあります。
このような消費の冷え込みは経済全体の成長を鈍化させ、それが巡り巡って企業の業績や個人の収入に影響を及ぼし、さらには日銀の追加利上げの判断を躊躇させるという、複雑なフィードバックループを生み出す可能性があるのです。
住宅購入者は、こうした大きな経済のうねりの中にいることを認識する必要があると言えるでしょう。
結論、『現在の政策金利の上昇は、まだ、正常な状態に戻す治療中!』
以上のように、金利が上がって欲しくない我々と、金利を上げて経済を正常な状態に戻したい日銀、それに輪をかけるトランプ関税等の不確実性・・・、一筋縄ではいきません!
ただ、今までが異常であったこと、正常に戻れば、金利も上がるけど賃金も上がる(ハズ)と思えば、この先を少しは冷静に見られるかもしれません。しっかりと賃金も上がる「良いインフレ」になるよう日銀の舵取りに期待したいところです。
結論としては、『まだ、正常な状態に戻す治療中!』ということを認識し、まだ起こり得る変化に一喜一憂しないようにしなければなりません。
我々にとってのリスクは、金利上昇で少なくないのも事実です。でも、金利は上がり続けることはありません。上がったり、下がったりする正常な状態に戻そうとしているだけです。まだ、バブルがはじける前、日本経済が今より元気だった頃、過去にさかのぼると10年で上昇と下降の山が二度できていました。当時は、変動金利で7%、8%という時もありましたが、その時と違い、日本の人口は減少しているし、経済もイケイケではありません。日銀も微妙な舵取りをしています。煽るような発信に惑わされず、程よい着地点を期待しましょう!
とりあえず、日銀が言っているのは『あと1%』程度、政策金利1.5%、銀行の店頭金利2.5%程度で、そこから個人個人の優遇金利幅のディスカウントがある、ここに向かっていることだけは間違いないということです。そのようになるかは、わかりませんが!
ご参考まで。