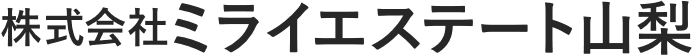『日本の住宅政策は、まずは〝持ち家〟から』

2019年、金融庁の報告書が投じた「老後2000万円問題」という一石は、日本社会に大きな波紋を広げました。多くの国民が自らの老後に漠然とした不安を抱き、「年金だけでは暮らしていけないのか」と騒然となったことは、記憶に新しいでしょう!
しかし、あの衝撃的な数字の裏には、見過ごされがちな「大前提」が隠されていました。そして、その前提を紐解くと、国が私たち国民に送る極めて明確なメッセージが浮かび上がってきます。それは、『日本の住宅政策は、まずは〝持ち家〟から』という、揺るぎない方針です。
ここでは、あの「2000万円」という数字は何だったのかを解き明かし、なぜ、一般庶民にとって「持ち家」という選択が、老後の生活を防衛する上で極めて合理的な戦略なのかを検証していきます。
目次
1、「老後2000万円」の知られざる大前提
まず、あの「2000万円」という数字が、どのような家庭をモデルに算出されたのかを知る必要があります。金融庁の報告書が想定したモデルケースは、以下の通りです。
世帯構成: 夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみの無職世帯
- 収入: 公的年金が主たる収入源(当時のモデルで月収約21万円)
- 支出: 平均的な消費支出(月約26万円)
- 住居: 持ち家(住宅ローン完済済み)
毎月約5.5万円の赤字が30年間続くと、合計で約2,000万円が不足する、というのが「2000万円問題」の計算根拠です。
ここで最も重要なポイントは、このシミュレーションが「持ち家」を大前提としている点です!支出に含まれる住居費は、固定資産税や修繕費といった持ち家の維持費(月額1万5千円程度)であり、賃貸住宅の家賃は一切考慮されていません!!
つまり、あの2,000万円という数字は、すでに「住む場所」を確保し、ローンという最大の負債を解消した世帯ですら直面する不足額だったのです。
2、もし「賃貸」なら?老後資金は4,000万円超えの衝撃
では、もし生涯を賃貸住宅で暮らす場合、老後資金は一体いくら必要になるのでしょうか。
総務省の統計によれば、高齢者世帯の平均家賃は月額約5.6万円です。この家賃を老後の30年間(360ヶ月)払い続けると仮定すると、それだけで約2,016万円もの追加費用が発生します!数年ごとの契約更新料も考慮すれば、その額はさらに膨らむでしょう。
これを先の「2,000万円」に単純に上乗せすると、賃貸派の老後必要資金は、一気に4,000万円を超える計算になります。これは、もはや個人の努力だけで乗り越えるには、あまりにも厳しい数字です。
3、厚生年金か国民年金か。残酷なまでの年金格差!!
さらに、この問題には「年金の種類」という、もう一つの大きな変数が存在します。
「2,000万円問題」のモデル世帯の年金収入は、夫が会社員(厚生年金)、妻が専業主婦(国民年金)という、かつての「標準世帯」を想定したものでした。
しかし、働き方が多様化した現代において、このモデルは決して万人に当てはまりません。
厚生労働省のデータに基づき、より現実的なシミュレーションを行うと、残酷なまでの格差が浮かび上がります。
- 夫(会社員)+妻(専業主婦)の場合:
年金収入の合計は月額約22.2万円。平均的な支出(月約28.7万円)を差し引くと、毎月6万円以上の赤字となり、老後に必要な資金は約2,300万円に膨れ上がります。 - 夫婦ともに自営業(国民年金)の場合:
年金収入の合計は月額約11.6万円。生活費を大幅に切り詰めない限り、赤字額はさらに拡大し、必要な老後資金は青天井となります。
これらのシミュレーションが示すのは、日本の公的年金制度が、現役時代に厚生年金に加入し、かつ老後の住居費負担がない「持ち家・ローン完済世帯」を暗黙の前提として設計されているという、紛れもない事実です。
結論、『日本の住宅政策は、まずは〝持ち家〟から』
賃貸では老後資金が4,000万円以上必要になるリスク。年金制度が内包する構造的な格差。これらの厳しい現実を前に、国は一貫した政策で「解」を示し続けています。それが、徹底した持ち家取得の推奨です。
- 住宅ローン控除: 年末のローン残高の0.7%を所得税から控除する、強力な税制優遇。
- 補助金制度: 省エネ性能の高い住宅の取得に対し、最大で160万円もの補助金が支給される「子育てグリーン住宅支援事業」など、手厚い支援策。
- 固定資産税の軽減措置: 住宅が建っている土地の税負担を最大6分の1にまで軽減する特例。
- 不動産取得税:購入時に一度だけかかる、住宅用であれば税率が軽減され、新築住宅なら課税額から最大1300万円が控除される。
これらの恩恵は、すべて「持ち家」を選択した者だけが享受できるものです。国は、税制と補助金という最も強力なツールを用いて、国民を「持ち家」へと誘導しているのです。
もちろん、持ち家には修繕費や固定資産税といった継続的なコストや流動性の低さといったリスクも伴います。しかし、老後の住居費という最大の支出を現役時代に前倒しで解消できるメリットが大きいのも事実!ローン完済後の家は、売却して老後資金に充てることも、リバースモーゲージで生活費を捻出することも可能な、まさに「最後の切り札」となり得ます。
「老後2000万円問題」は、私たちに老後の厳しさを突きつけただけでなく、日本の社会構造における「住まいの最適解」を逆説的に示しました。国の政策という流れに賢く乗ること、それこそが、私たち一般庶民がこの不確実な時代を生き抜くための確かな羅針盤なのかもしれません。NISAやiDeCo、この流れにも乗る必要がありそうです!
日本の住宅政策の根幹は、今も昔も、まずは〝持ち家〟からなのです。
ご参考まで。